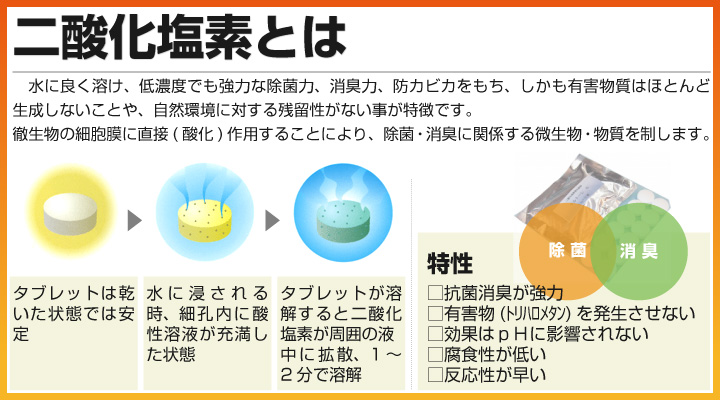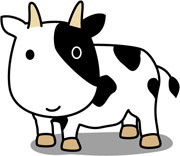効果的な蹄浴による費用の低減と跛行の減少
効果的な蹄浴による費用の低減と跛行の減少
オルトゥロ・ゴメス博士、獣医師
ジンプロコーポレーション
農場において、趾皮膚炎やヒゲイボとして知られている感染性の蹄病によって引き起こされる経済損失は、大きなものとなっています。これら感染性蹄病の新規発生の予防と、慢性病変をコントロールするために、蹄浴が一般的に行われています。趾皮膚炎はすぐに病態が変化していく疾病です。わずか10日間で小さな潜在性の病変(直径2cm以下)から進行性の急性潰瘍病変(直径2cm以上)に進行してしまいます。アメリカでは治療のために$300/頭かかるとされているために、予防が非常に重要です。
忘れてはならない蹄浴の目的
蹄浴の目的は感染性の蹄病の予防とコントロールであることを決して忘れないでください。臨床症状が出ている牛の治療のために蹄浴を用いるわけではありません。農場において、すでに趾皮膚炎治療のために相応のお金をかけているとしても、効果的な蹄浴プログラムを確立することで、慢性病変が再度臨床病変に進行することを防いだり、健康牛の新規罹患を予防することが期待されます。蹄浴プログラムの中で、デザイン、設置場所、管理を最良にするよう注力することで、蹄浴を行う頻度を減らしたり、治療費用を大きく減らすことが出来ます。
牛の肢蹄の問題を予防する上でデザイン、設置位置、管理方法が重要
蹄浴は農場において、個別の牛1頭1頭に対して行う処置ではなく、群全体に対する対策として扱われます。蹄浴に用いる薬剤の検討よりも、蹄浴槽のデザイン、設置位置、管理方法がより重要な検討項目です。
蹄浴の効果を高めるために忘れてはいけないポイント
・パーラーの戻り通路のように、牛が日常的に通過する場所の水平な地面に蹄浴槽を設置する。全頭の全肢が、蹄浴槽全体を使って薬液に浸かることを確認する。
・蹄浴槽は長さ3〜3.7m、幅0.5〜0.6m、深さ25cmのものが推奨される。
・薬剤が好発部位に十分に付着するために、薬液の深さは最低でも10cm以上とする。
・下肢の衛生スコアに基づいて、各週で日を開けずに蹄浴を行う。下肢の衛生スコアは、蹄浴頻度を決める目安となる。汚れている牛が多い場合、より蹄浴頻度を増やさなければならない。
・現在多くの農場において、一般的には100〜300頭が通過したら蹄浴の薬液を交換している。牛体の衛生状態や天候、薬剤の種類や濃度によって、薬液の交換頻度は異なる。
・新しい薬液を補充するタイミングを調整し、各群の牛たちが新鮮な薬液に肢を浸けることが出来るようにする
・新しい薬液を投入する前に、古い薬液を完全に排水し、水で蹄浴槽を洗う
・蹄浴槽を通過後、清潔で乾燥した場所を歩かせる
・薬液を用いない日でも、石鹸浴(水100リットルに対して、洗剤1リットルを投入)を行うことで、衛生状態を保つ。
・固定式の蹄浴槽を用いる場合、蹄浴を行わない日は、蹄浴槽上を歩かない迂回路を設けることが推奨される。

上記のポイントを満たす様に蹄浴槽のデザイン、設置場所、管理方法を検討する事が、最良で効果的な蹄浴プログラムを運用する事に繋がります。それによって趾皮膚炎のような感染性の蹄病の予防及び治療にかかる費用を共に減らすことが出来ます。
引用記事:ZINPRO